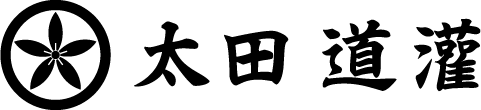作家尾崎氏の連載するブログ「道灌紀行は限りなく」
最新記事3件を表示しています。
詳細は「道灌紀行は限りなく」をご覧ください。
道灌紀行は限りなく
2025/03/09
1.太田氏丹陽より相模へ 太田道灌の詩友万里集九(ばんりしゅうきゅう)の漢詩文集「梅花無尽蔵(ばいかむじんぞう)」(1506年)の中に江戸城静勝軒(じょうしょうけん)の詩板のために書いた「静勝軒銘詩并序(じょうしょうけんめいしならびにじょ)」があり、その中に道灌の出自について次のように記されています。「太田左金吾公道灌は、その先はすなわち丹陽のひとなり。しかるに五、六葉の祖、はじめて相州に家す」と。 『新編武蔵風土記稿』(1830年)相模国久良岐(くらき)郡之六太田村にい..
2025/01/15
「歴史は常に過去と折り重なって展開する」とは、「享徳の乱」の著者峰岸純夫氏の言葉です。太田道灌の「非業の最期」をもたらした、「京都方」と「関東方」の争いの経過を、現地を訪問しながらやや詳しくたどってみます。太田道灌は1432年(永享4年)に生まれ、鎌倉で幼少時代をすごしました。後に「享徳の乱」の真っただ中を駆け抜けた道灌は、そのすべてを聞くか見ていたことでしょう。 太田道灌の時代には、京都に室町幕府があり、その配下に鎌倉の鎌倉府がありました。そして鎌倉府の鎌倉公方の下に関..
2024/10/10
西武新宿線の上石神井駅より徒歩17分あるいはJR中央線の荻窪、西荻窪からバスで10数分も走ると、東京都杉並区の井草八幡宮の大鳥居の近傍へきます。今は市街地の真っただ中ですが、ほど遠くないところに善福寺池もあるので往時は、この辺りが鄙びた、江戸の水源地であったと推測されます。 赤い大鳥居をくぐるとやや長い参道がつづきます。この参道で5年に一度、祭りの日に流鏑馬(やぶさめ)神事が行われます。参道をぬけると広場があり本殿や神楽殿、文華殿などいろいろな建物と頼朝手植えの松が並んでい..